 北海道の自然紹介「花とマルハナバチ」
北海道の自然紹介「花とマルハナバチ」 北海道の自然紹介「花とマルハナバチ」
北海道の自然紹介「花とマルハナバチ」ぶん:丹羽真一 え:渡辺展之
前回はマルハナバチの体の特徴や種間のすみわけなどについて紹介しました。今回はマルハナバチの一年の生活についてみていきたいと思います。ヤナギの花が咲き出すころ、まだまだ北海道は寒いですが、マルハナバチも見られるようになります。花好きの人はぜひマルハナバチにも興味を持って観察して下さい。
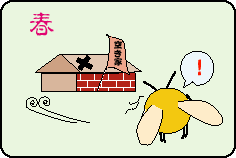 根雪が消えるとまもなくマルハナバチは目覚めます(ひがし大雪の糠平ではゴールデンウィーク前後)。冬を乗り越えて地上に出てきたマルハナバチの女王は、とりあえず花から蜜を吸って空腹を満たさなければなりません。この時期の原野は森林と比べ早く雪が解けるものの殺風景な景色が広がるだけで、まだ本当にわずかな植物が花を咲かせているにすぎません。春一番に咲く花は何と言ってもヤナギです。原野にはたいていどこでもヤナギがたくさん生えていて、特に早く咲き出したエゾノキヌヤナギの樹には驚くほどたくさんのマルハナバチが集まっています。高さ4mくらいの樹に20〜30頭もいたのを見たことがあります。ハチ以外にもアブの仲間が何百、何千頭と来ています。ヤナギは風によって花粉を媒介する「風媒花」と言われてきましたが、蜜や花粉を出して昆虫にも花粉を運ばせているのです。
根雪が消えるとまもなくマルハナバチは目覚めます(ひがし大雪の糠平ではゴールデンウィーク前後)。冬を乗り越えて地上に出てきたマルハナバチの女王は、とりあえず花から蜜を吸って空腹を満たさなければなりません。この時期の原野は森林と比べ早く雪が解けるものの殺風景な景色が広がるだけで、まだ本当にわずかな植物が花を咲かせているにすぎません。春一番に咲く花は何と言ってもヤナギです。原野にはたいていどこでもヤナギがたくさん生えていて、特に早く咲き出したエゾノキヌヤナギの樹には驚くほどたくさんのマルハナバチが集まっています。高さ4mくらいの樹に20〜30頭もいたのを見たことがあります。ハチ以外にもアブの仲間が何百、何千頭と来ています。ヤナギは風によって花粉を媒介する「風媒花」と言われてきましたが、蜜や花粉を出して昆虫にも花粉を運ばせているのです。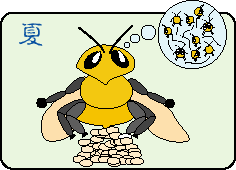 働きバチが羽化してくると、それまで蜜や花粉の採集と育児をすべて一人でこなしてきた女王バチは、産卵と育児に専念するようになります。外仕事は働きバチが担うようになり、さらに働きバチが多くなると育児もするようになるので女王はますます産卵に集中します。
働きバチが羽化してくると、それまで蜜や花粉の採集と育児をすべて一人でこなしてきた女王バチは、産卵と育児に専念するようになります。外仕事は働きバチが担うようになり、さらに働きバチが多くなると育児もするようになるので女王はますます産卵に集中します。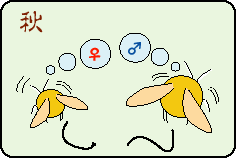 夏から秋にかけて、巣からオスと新女王バチがでてきます。マルハナバチに限らず、家族(コロニー)を作る昆虫では雄と雌を産み分けています。マルハナバチでは受精卵からは雌(働きバチと新女王バチ)が、未受精卵からは雄が産まれます。新女王や雄バチが出てくるころになると、もはや新しい働きバチは産まれなくなり、やがて女王も死んで家族は解体します。晩秋の朝にはマルハナバチの新女王バチが、クローバーやセイヨウタンポポの花に掴まって朝露に濡れながら太陽が上がってくるのを待っています。オスバチと新女王は、巣を離れてそれぞれに相手をみつけて交尾します。オスは交尾が終わると、そのまま死にます。新女王はおなかのタンクに冬越し用の蜜をたっぷり貯えて、冬眠の準備に入ります。
夏から秋にかけて、巣からオスと新女王バチがでてきます。マルハナバチに限らず、家族(コロニー)を作る昆虫では雄と雌を産み分けています。マルハナバチでは受精卵からは雌(働きバチと新女王バチ)が、未受精卵からは雄が産まれます。新女王や雄バチが出てくるころになると、もはや新しい働きバチは産まれなくなり、やがて女王も死んで家族は解体します。晩秋の朝にはマルハナバチの新女王バチが、クローバーやセイヨウタンポポの花に掴まって朝露に濡れながら太陽が上がってくるのを待っています。オスバチと新女王は、巣を離れてそれぞれに相手をみつけて交尾します。オスは交尾が終わると、そのまま死にます。新女王はおなかのタンクに冬越し用の蜜をたっぷり貯えて、冬眠の準備に入ります。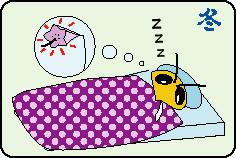 マルハナバチは冬が来る前に冬眠に入ります。冬眠するほかの動物と同様、地面の中にもぐることが多いようです。雪の下はいくらかでも寒さを避けることができるからでしょう。北海道、とくに東大雪のように寒い地方では、冬眠は8ヵ月近くにおよび、その間に死ぬ個体も多いと考えられます。早春のマルハナバチ女王の個体数は年によってかなり変動しますが、初冬から早春までの間にどれだけ生き残れるかということも影響していると思われます。
マルハナバチは冬が来る前に冬眠に入ります。冬眠するほかの動物と同様、地面の中にもぐることが多いようです。雪の下はいくらかでも寒さを避けることができるからでしょう。北海道、とくに東大雪のように寒い地方では、冬眠は8ヵ月近くにおよび、その間に死ぬ個体も多いと考えられます。早春のマルハナバチ女王の個体数は年によってかなり変動しますが、初冬から早春までの間にどれだけ生き残れるかということも影響していると思われます。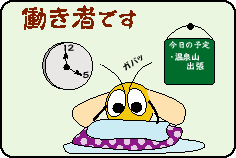 マルハナバチは飛翔能力が高く、かなり広い範囲を行動していると思われます。マルハナバチの生態を調べたハインリッチは、「時速11〜20kmで飛翔し、…必要なら少なくとも5km」は移動すると述べています(ハインリッチ1979)。私が観察している温泉山では、春先にたくさんいたエゾナガ・エゾトラ・アカマルは夏になると見られなくなります。これらのマルハナバチは、山に蜜が豊富なときだけ、おそらくはふもとから遠征(3〜5km)してきているのではと私は思っています。
マルハナバチは飛翔能力が高く、かなり広い範囲を行動していると思われます。マルハナバチの生態を調べたハインリッチは、「時速11〜20kmで飛翔し、…必要なら少なくとも5km」は移動すると述べています(ハインリッチ1979)。私が観察している温泉山では、春先にたくさんいたエゾナガ・エゾトラ・アカマルは夏になると見られなくなります。これらのマルハナバチは、山に蜜が豊富なときだけ、おそらくはふもとから遠征(3〜5km)してきているのではと私は思っています。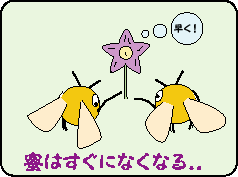 性質のおとなしいマルハナバチは、同じ植物上で別の個体と鉢合わせになっても相手を押しのけたりけんかになったりすることはまずありません(なわばりも持たない)。これについてハインリッチは、一見何の争いもないように見えるが実際にはほかの個体より少しでもたくさんの蜜や花粉を集めねばならないというし烈な競争があると説明しています。つまり、けんかする暇もないほど忙しいというのです。そう言われると、マルハナバチの忙しそうな行動も理解できます。シャクナゲのようにたくさん蜜を出す植物でも自然状態ではほとんどの花がハチによって空(から)にされていますが、このことも「蜜採り競争」の激しさを物語っています。
性質のおとなしいマルハナバチは、同じ植物上で別の個体と鉢合わせになっても相手を押しのけたりけんかになったりすることはまずありません(なわばりも持たない)。これについてハインリッチは、一見何の争いもないように見えるが実際にはほかの個体より少しでもたくさんの蜜や花粉を集めねばならないというし烈な競争があると説明しています。つまり、けんかする暇もないほど忙しいというのです。そう言われると、マルハナバチの忙しそうな行動も理解できます。シャクナゲのようにたくさん蜜を出す植物でも自然状態ではほとんどの花がハチによって空(から)にされていますが、このことも「蜜採り競争」の激しさを物語っています。
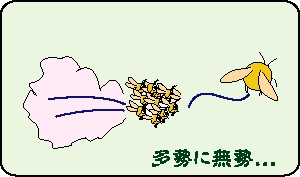 蜜を取る能力や花との相性によって競争力に差がある時、よい餌(花)は強い方の種が独占してしまうという報告があります。ボウワース(Bowers 1985)という人は、アメリカ・ユタ州の亜高山帯の草原で生活するマルハナバチ2種の競争力を比べました。それによると、それぞれ単独に生活しているときは全く同じような花を選んでいる2種のマルハナバチが、一緒になったとたん一方の種がよい花を独占し、もう一方は蜜の少ない花に変えざるを得なくなりました。このような競争力の差は、体格や飛翔力の違いではなく、圧倒的な働きバチの数の違いによるものでした。「人海作戦の賜物」だったのです。ではなぜそんなにも数が違うのかと言えば、春の目覚めの時期に3週間もの開きがあるためで、早く冬眠から起きた方が多くの働きバチを生み育てることができるのです。ただし、早春は季節外れの雪や霜のために死んでしまう危険も多く、早く起きることがいつもいいとは限りません。
蜜を取る能力や花との相性によって競争力に差がある時、よい餌(花)は強い方の種が独占してしまうという報告があります。ボウワース(Bowers 1985)という人は、アメリカ・ユタ州の亜高山帯の草原で生活するマルハナバチ2種の競争力を比べました。それによると、それぞれ単独に生活しているときは全く同じような花を選んでいる2種のマルハナバチが、一緒になったとたん一方の種がよい花を独占し、もう一方は蜜の少ない花に変えざるを得なくなりました。このような競争力の差は、体格や飛翔力の違いではなく、圧倒的な働きバチの数の違いによるものでした。「人海作戦の賜物」だったのです。ではなぜそんなにも数が違うのかと言えば、春の目覚めの時期に3週間もの開きがあるためで、早く冬眠から起きた方が多くの働きバチを生み育てることができるのです。ただし、早春は季節外れの雪や霜のために死んでしまう危険も多く、早く起きることがいつもいいとは限りません。